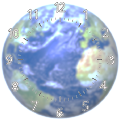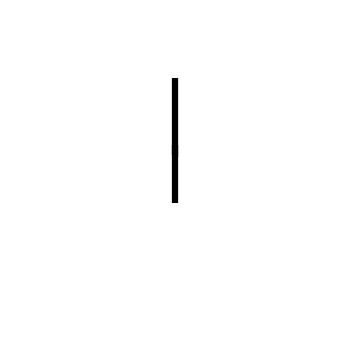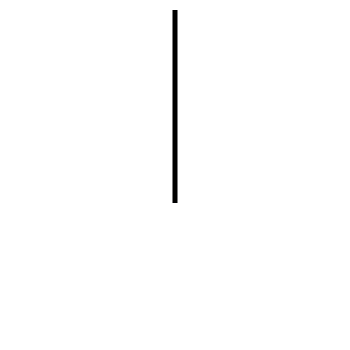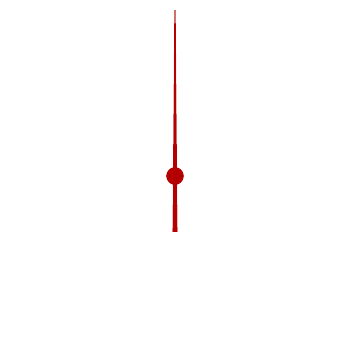May.02.2019
 åºèª3ã¶æç¨åã横æµã®ãã¼ã¹ãã¼ãã»ã³ã¿ã¼ã«éãã¡ã³ãã¼ã«ãã£ã¦ç»å±±é¨ãçºè¶³ãããé¦æ¸¯ããã·ã³ã¬ãã¼ã«ã§åæµããã¾ã§ç´1é±éã®éãè¹ã«æ®ãã¡ã³ãã¼ã¨ã¯é¢ãé¢ãã§æ§åãããããªãã£ãããã3人ã§ããã³å³¶ãã¾ãããã¨ã«ãªãå¬ããã£ãã
åºèª3ã¶æç¨åã横æµã®ãã¼ã¹ãã¼ãã»ã³ã¿ã¼ã«éãã¡ã³ãã¼ã«ãã£ã¦ç»å±±é¨ãçºè¶³ãããé¦æ¸¯ããã·ã³ã¬ãã¼ã«ã§åæµããã¾ã§ç´1é±éã®éãè¹ã«æ®ãã¡ã³ãã¼ã¨ã¯é¢ãé¢ãã§æ§åãããããªãã£ãããã3人ã§ããã³å³¶ãã¾ãããã¨ã«ãªãå¬ããã£ãã
 George Town (ã¸ã§ã¼ã¸ã¿ã¦ã³) ã§ãªã¾ã¼ãã¦ã§ã¢ãè³¼å
¥ãã¦çæ¿ããBatu Ferringhi Beachï¼ããã¥ã»ãã§ãªã³ã®ãã¼ãï¼ã¸åãã£ããããããã¼ãã«ä¹ã£ãããæ³¢ãæ¥ãã¨é£ã³è·³ãã¦éã³ãä¸ããéã¯ã©ã²ã®æ´ç¤¼ãåããã
George Town (ã¸ã§ã¼ã¸ã¿ã¦ã³) ã§ãªã¾ã¼ãã¦ã§ã¢ãè³¼å
¥ãã¦çæ¿ããBatu Ferringhi Beachï¼ããã¥ã»ãã§ãªã³ã®ãã¼ãï¼ã¸åãã£ããããããã¼ãã«ä¹ã£ãããæ³¢ãæ¥ãã¨é£ã³è·³ãã¦éã³ãä¸ããéã¯ã©ã²ã®æ´ç¤¼ãåããã
Little Indiaï¼ãªãã«ã¤ã³ãã£ã¢ï¼ã§ã¯ããã¿ãã¥ã¼ã«ãã©ã¤ããåºèªåã«GoProãè³¼å
¥ããTåããç´ æµãªQuickStoriesã«ä»ä¸ãã¦ãããã
- Local time May 2 (Thu) 20:30
April.26.2019
ã«ã³ãã¸ã¢å¤§ä½¿é¤¨ã®ãã¼ã ãã¼ã¸ããæç²ããã¨ããã·ã³ã°ã«ãã¶ã¯ãæå¹æéå
ã®1åéãå
¥å½ãçºè¡æ¥ãã3ã¶ææå¹ãæ»å¨ã¯1ã¶æã¾ã§ã§ãããã¨ãããããã«ããã«ã³ãã¸ã¢å
¥å½æ¥ãã1ã¶æã¾ã§æ»å¨å¯è½ã§ãããã¨ããã
注ç®ãããã®ã¯ãå
¥å½ã«é¢ãã¦ã¯æå¹æéã3ã¶æã¨è¬³ã£ã¦ããããåºå½ã«ã¤ãã¦ã¯å
·ä½çãªè¨è¼ããªãç¹ã§ãæå¹æéã¯ãå
¥å½ããã¾ã§ãçºçµ¦ãã3ã¶æéãå
¥å½ããããã®æ¥ãã1ã¶æéã§ããã¨èããã®ããµã¤ãã ããã
å®éã1æ28æ¥ã«æ±äº¬ã®ã«ã³ãã¸ã¢å¤§ä½¿é¤¨ã訪ããéãå
¥å½äºå®æ¥ã4æ25æ¥ãåºå½äºå®æ¥ã¯çºè¡æ¥ãã3ã¶æãè¶
ãã4æ29æ¥ã¨ãã¦ãã¶ãç³è«ããããåé¡ãªãçºçµ¦ãåãã¦ããã
ã¨ãããé¦æ¸¯åºå½ã«ããã¦ããã¶ã«å°åãããæå¹æéãè¦ãã¨ã¢ã©ã¤ã³ã®ã°ã©ã³ãã¹ã¿ããæ°ãã復路便ã®æä¹æã«ã¯ãã¶ãç¡å¹ã§ããã¨ä¸»å¼µããæä¹å¸ã®çºå¸ãæãã ã
ãã£ããããªã°ããªã
ããããããã¨ããã¶ã«ã¯æ¸¡èªå
ã®å½ã®å
¥å½å¯©æ»ãåããããæå¹æéã¨ããã®å½ã®æ»å¨ã許ãããæ»å¨æéï¼å¤å½ããæ¥æ¬ã«æ¥ãå ´åã¯å¨çæéï¼ããããæ»å¨æéä¸ã«ãã¶ã®æå¹æéãåãã¦ãæ³çã«ã¯åé¡ãªãããã ããçºçµ¦ããå½ã«ãã£ã¦æå³ãå¹åã«éãããã£ãããããããå
æ¹ã誤ã£ã解éãããã®ã§ããã
確èªãã¦çºå¸ã«è³ãããæ³å®ãã¦ããªããã©ãã«ã«ã¡ãã£ã¨æ°ã¾ããã£ãã
ãã®å¾Phnom Penhï¼ããã³ãã³ï¼ã®å
¥å½å¯©æ»ã«ã¦ããã¹ãã¼ãã«25 APR 2019ãUNTIL 25 MAY 2019ã¨æ¼å°ãããæ»å¨ã«æ¯éãªããã¨ã¯ç¢ºèªã§ããã
- Local time April 26 (Fri) 01:00
April.25.2019
ä¸æ¨æ¥ï¼23æ¥ï¼ãè¹å
çæ´»ãææ義ãªãã®ã«ããè¹å
ãã¼ã ã®ç´¹ä»ãè¡ãããâ1æéã®æ差調æ´ããã£ãã
ãã¾ã«PBã¯è¥è
ãã¿ãã§åããã¦ããã¨æãéãããã¦ãã人ãããããããã¯èª¤ãã§ãããä½æ
ãªããèªåãã¡ã§è¹ãåºããä¸çãè¦ããã¨å§ããããã®ãPBã§ããã
4æ21æ¥ãã³ãã³ããå§ãã¨ããã¹ãªã©ã³ã«å½å
ã®8ã«æã§åæççºãããããã258人ã®æ»äº¡è
ã500人ã®è² å·è
ãåºãã
å
æ¦çµçµãã10å¹´ã«å½ããããä»ãªããæ°æãå®æéã®åé¡ã解決ãã¦ããªããã¨ãçæããã
æ¬è¹ã¯5æ5æ¥ã«ã³ãã³ãå¯æ¸¯ãäºå®ãã¦ããããããã«ããèªè·¯ãå¤æ´ãã5æ2æ¥ããã¬ã¼ã·ã¢ã®ããã³å³¶ã«å¯æ¸¯ãã¦ãã¼ããµã¤ãã¸åããã
 åãã¦é¨ãéã£ãããåå¾ã«ã¯æ¥ãå·®ãããã¤ãã®ããã«æ¥ãæµ´ã³ï¼ãã¸ã ã«éã£ãã
åãã¦é¨ãéã£ãããåå¾ã«ã¯æ¥ãå·®ãããã¤ãã®ããã«æ¥ãæµ´ã³ï¼ãã¸ã ã«éã£ãã
è¹å
ã®ãã¼ã¹ãã¼ãã»ã³ã¿ã¼ããªã¼ãã³ãç©åãææ¡ãå¯æ¸¯å°ã¬ã¤ãããã¯ï¼ã¿ãã¬ããï¼ãæãªã¨ãèªãããã¨ããããé¨å¡ç»é²ãã¦ããã
Regency Restaurantã§ã¯ãªãã¼ã¿ã¼ã®éããè¡ãããããåºå¸ãã¦ããªãã
â»åçã¯ã¤ãã³ãã®éå¬ãªã©ã«ããä»ã®å©ç¨è
ãããªãæã«æ®å½±ããã¦ãã¾ãã
é¦æ¸¯ããã«ã³ãã¸ã¢ã¸æ
ç«ã¤åã«ãæ´ä¸ã¯ã¾ããããLidoã®ããªã¼ã¹ãã¼ã¹ã§è¡ããããã®å¾æ´ä¸å±
é
å±æ³¢ã¸ãã§é£²ã¿ããã¼ãã²ã¼ã ã®ã«ã¿ã³ã«åå ãåå1æéã解æ£ããã
- Local time April 25 (Thu) 02:00
April.23.2019
ååä¸ãã«ã³ãã¸ã¢ã®å°é·åé¡æ¤è¨¼ãã¢ã¼ã¸åå ããã¡ã³ãã¼ã®é¡åããããããBuffet Panoramaï¼ãããã§ããã©ãï¼ã«ã¦ã©ã³ãããã
ãã¤ã¯ã«ã³ãã¸ã¢ãå°é·ã®ãã¨ã«ã¤ãã¦ã¯ã人ä¼ã«è´ããããNGOãJAICAã®å ±åæ¸ãèªãã ã ãã§ãç¥ã£ã¦ããããã§ç¥ããªãã
3å¹´åã«ç¬¬92åå°çä¸å¨ã«ä¹è¹ãã以éãåéæ´»åã«æºããããã«ãªããèªåã®ç®ã§ç¢ºããããã¨ãä¸å¯æ¬ ã«æããã
è¹é·ä¸»å¬ã®ã¦ã§ã«ã«ã ã»ã¬ã¢ãã¼ãããã横æµã¡ã³ãã¼ã§è¹é·ã¨è¨å¿µåçãæ®ãã
ã¦ã§ã«ã«ã ãã£ãã¼ã®ã³ã¼ã¹æçã¨ä¸¦è¡ããLidoï¼ãªãï¼ã§æä¾ããã¦ããã«ã¬ã¼ã©ã¤ã¹ãé£æ¬²ãããããç·åçµã¯Regency Restaurantï¼ãªã¼ã¸ã§ã³ã·ã¼ ã¬ã¹ãã©ã³ï¼ã¸æ¢¯åããã
æ´ä¸ã·ããã¯Greatest Showmanãã«ã¼ãã²ã¼ã ã®UNOï¼ã¦ãï¼ã«å¤¢ä¸ã«ãªãã解æ£ããã®ã¯åå2æéãã§ãã£ãã
 |
横æµãåºèªãã¦ããæ¦ãæ´å¤©ãç¶ãã¦ãããããããã§ã¢ã§ã®æ¥ç¼ããæ¥èª²ã«ã
|
bow tieï¼ãã¦ã¿ã¤ï¼101å¹ããã¡ããï¼æã¬ããå°éåºããã¾ãã¬ãà Disneyï¼ã®æãæ¹ã¯ã
- æã¬ãããï¼ã¤ã«æããããã«ï¼ã¤ã«ï¼è³ã¯ä¸ã¸ï¼æãã¾ãã
- 端ãã12cmããããï¼åæããã²ã£ããè¿ãã¦ãæ®ãã®é¨åãï¼ã¤æããã¦ãç´è§ã«ãªãã³ãé ããä¸æ¹ã®ç«¯ããªãã³ã®è£ã®çµã³ã«éãã¾ãã
|
|
April.20.2019
4æ20æ¥ï¼åï¼ã横æµã¯æããæ¥ã®ç½ãããªç©ºæ°ã¨æ¥å·®ãã«å
ã¾ããã
4ã¶æåã«ã¯ãã®ããããããåãããã«ã¿ãªã¨ã¿ããã®é«å±¤ãã«ç¾¤ãªã©ãçºãã¦ããã§ããããå
ã®ã¯ã«ã¼ãºã«ä¹è¹ããã¡ã³ãã¼ãããæºé¢ã®ç¬é¡ãæºãè¦éãã«æ¥ã¦ãããã®ããã¨ã¦ãå¬ããã£ãã
åã®ãã£ãã³ã¯ååãé²ç«å£ã«éã¦ããã7ãããè¹å°¾é段ä»è¿ã«ããã
 横æµã§ãã©ã³ãã£ã¢æ´»åããå
±ã«éãããã¡ã³ãã¼ãããããã¦é£äºã«èªã£ãããé¨å±ã訪ãã¦æ¥ãªããã°ã人ã«ä¼ããã¨ãå°ãªãã
横æµã§ãã©ã³ãã£ã¢æ´»åããå
±ã«éãããã¡ã³ãã¼ãããããã¦é£äºã«èªã£ãããé¨å±ã訪ãã¦æ¥ãªããã°ã人ã«ä¼ããã¨ãå°ãªãã
å½¼ãã®ãã£ãã³ãã5ãããåæ¹ãã¯ããã7ãããã®ãã¤ã¼ã¢ã©ã¦ã³ã¸ä¸ã5ãããå¾æ¹ã6ããããªã©ã²ã¨ã¤ã®å ´æã«ã¾ã¨ã¾ã£ã¦ããããã§ã¯ãªããæ¥è¨ãã¾ãããã¨ã«ãªã£ãã
3å¹´åã¯beatãæµã大å¢ã®è¥è
ãèªè·¡ãèã«è¸ã£ããé£ã³è·³ãããããããã§ããªãããããè¹å°¾ã®æ¯åããã大ããã諸è¬ã®äºæ
ã§ä½¿ããªããã£ãã³ãå
ããªããåå¨ããã
å¿é
ããã£ãããèå±±ã§ã®ããã¯å
¥ãã«ãããè¹å
¨ä½ãè¦éãããããªè¯ãã³ã³ãã£ã·ã§ã³ã«ãªã£ã¦ãããç®è¦ã¾ããèºé²ãéããä¸å½ã®æè¡åã«é©åããã
â»ãããã§é£ã³è·³ãããã¨ã¯ãç¾å¨ã¯ã§ãã¾ããã
April.10.2019
ä¹è¹ãç®æãã¦ãã©ã³ãã£ã¢æ´»åã«åå ããä¸å®ã®ç®æ¨ãéæãã人ãªã©ã«æä¸ãããåæ¥è¨¼æ¸ï¼å°çä¸å¨ã®å¤¢ã«åãã¦-16åç
§ï¼ãããã ããã
å
¨ã¯ãªï¼ä¹è¹æã«ç¸å½ãããã©ã³ãã£ã¢å²å¼ãæéä¸ã«éæ=ã¯ãªã¢ãããã¨ï¼ããããã§ã¯ãªãããå¤ãã®ã¡ã³ãã¼ã¨ãåªãããæã«ã¯å³ããããã¦ãããã¹ã¿ããã«æ¯ãããã風ã®å¹ãæ¥ãéªã®èãæ¥ãããã¹ã¿ã¼ãæ²åºãã¦ãããåºãéæãã¦ã¡ã³ã¿ã«ãéãã仲éã¨ã¨ãã«è¡¨å½°ãåãããªãã¦ãèããããªãã£ãã
åã¯å¿ã®ä½å¦ãã§æ°ããããæ°ã¹ã¤ããã欲ããã¦ãå°ãããã®ã§ã¯ãªãã ãããã
åãã®ä¸çã¯ããã»ã©é·ããã®ã§ã¯ãªããããã¤ã¾ãã¬äººçã¯éããããªãã
 ãããã4æ20æ¥ãããè¼ã仲ééã¨ãäºåº¦ç®ã®å°çä¸å¨ã«æ
ç«ã¡ã¾ãã
ãããã4æ20æ¥ãããè¼ã仲ééã¨ãäºåº¦ç®ã®å°çä¸å¨ã«æ
ç«ã¡ã¾ãã
ä»åæ
ãå
±ã«ããã¡ã³ãã¼ã«ã¯ãããã¯ãã¯ã·ã³ã°ã®ã¿ã¤ãã«ãä¿æãã3æ10æ¥å¾æ¥½åãã¼ã«ã«ã¦éå¬ãããBigbangã§ã1R2å11ç§TKOåã¡ãè¦ããç¾å½¹ã®ã¢ã¹ãªã¼ãããã¾ããï¼ãã®ã¼ãæããæããã¦ããã ãã¾ãããï¼
åã«ã¨ã£ã¦æ
ã¯ã家ã®ä¸ããããã ã«ä¿ã¡ãèªç±ã§ããç¶ããæ段ã§ãããã¾ããï¼å°çä¸å¨ã®å¤¢ã«åãã¦-12åç
§ï¼
ä»æ¥ï¼4æ10æ¥ï¼ã横æµãã1,359人ï¼ã®ä¹å®¢ãä¹ããä¸çä¸å¨ã«åºãJTBãã£ã¼ã¿ã¼ã®Sun Princessã¨ã¯ããã¥ã¼ã¨ã¼ã¯ã§ä¸¦ã³ã¾ãã
ãã£ã¨æ¥½ããæ
ã«ãã¦ã¿ãã¾ãã
February.04.2019
æ¥æ¬ã®ãã¹ãã¼ãã¯2018å¹´10æ9æ¥ç¾å¨ãä¸ç190ãå½ã«ãã¶ãªãã§æ¸¡èªã§ããããã«ãªãããã¶ãªãã§è¨ªãããã¨ã®ã§ããå½ãå°åã®æ°ã¯åç¬ä¸çä¸ã¨ãªãã¾ããã
ãã¹ãã¼ãã¯ãåå½æ¿åºãçºè¡ãè¡ããå½å¤ã«æ¸¡èªãã人ã«å½ç±ã身åã証æãããã®ã§ãã
対ãã¦ãã¶ï¼æ»è¨¼ï¼ã¯ã渡èªå
ã®å½ãçºè¡ãããæ»å¨è¨±å¯è¨¼ã§ãã
ESTAãETASã¯ãã¶ã§ã¯ããã¾ããããã¶å
é¤ããã°ã©ã ãæãã¾ããå°å
¥ããå½ãå¢ãã¦ãã¾ãã
101st Global Voyageã§ããã¶ããã¶å
é¤ããã°ã©ã ã®æç¶ããå¿
è¦ãªå½ã¯ããªã¼ãã¼ã©ã³ããå«ããã¨ãã«ã³ãã¸ã¢ãã¹ãªã©ã³ã«ãã¨ã¸ãããç±³å½ããã¥ã¼ãããªã¼ã¹ãã©ãªã¢ã§ãããããäºå¤§é¸ãããã¶ï¼ä»¥ä¸ããã¶å
é¤ããã°ã©ã ãå«ãï¼ã®æ°ãå端ãªãã§ãã(ç¬)
èªèº«ã§åå¾ã§ããå ´åã¯ææ°æã®æ¸é¡ãåãããã¾ããããã¶ãåå¾ã§ããææã該å½ãããã¶ã®ç¨®é¡ãæå¹æéãªã©ã¯èªåã§èª¿ã¹ãæ
è¡ä¼ç¤¾ã®æ
å½è
ã«ã確èªãã¦ãããªããã°ãªãã¾ããã
å人åå¾ããããã¶ã¯ã¤ã¬ã®ã¥ã©ã¼â»1ï¼ã§ãããããå
¥ç®¡æç¶ãã«ããã¦ãã®é çªãæå¾ã«ãªããã¨ãããã¾ãã
ETASã¯ãªã¼ã¹ãã©ãªã¢æ¿åºãå®æ½â»2ï¼ãã¦ããé»åæ»è¨¼ã«ãªãã¾ããããã®ã·ã¹ãã ã¯èªç©ºä¼ç¤¾ã®èªç©ºå¸çºå¸ã·ã¹ãã ããã¼ã¹ã¨ãã¦éçºããã¦ãã¾ããå¾ã£ã¦èªç©ºä¼ç¤¾ã®çºå¸ã·ã¹ãã ä¸ã§ãETASãç³è«ãåå¾ãããã¨ãã§ãã¾ããâ»3ï¼
â»1ï¼æ¬æ¥ã¯ãä¸è¦åãªãã¨ããæå³ã§ãããããä¾å¤ããæãã
â»2ï¼æ¿åºã®å
¬å¼ãµã¤ãã§ã¯ã·ã¹ãã å©ç¨æé20AUDãçºçãã¾ãã
â»3ï¼ä½ããèªç©ºä¼ç¤¾ã¯ç¾å¨ETASã®ç»é²ãµã¼ãã¹ãè¡ã£ã¦ããªããããå°ãã§ãè²»ç¨ãç¯ç´ãã¦åå¾ããããªã代è¡æ¥è
ã«ä¾é ¼ãã¾ãã
※4ï¼ã¹ãªã©ã³ã«ãæééå®ã§ãã¶å
é¤ï¼
January.20.2019
ãã¼ã¹ãã¼ãã®eco shipã2022å¹´ã®å°±èªäºå®ã«ãªãã¾ããã
eco shipã®ç¬¬1ååéãå§ã¾ã£ãã®ã¯ã第92åã®å°çä¸å¨ã決ããæºåãã¦ããæä¸ã§ããªãã¼ã¿ã¼éå®ã§ããã大åã®äººã¯ãã®ä¸ç¢ºå®æ§ï¼ãªã¹ã¯ï¼ã«ã¤ãã¦ãèªèããã¦ããããã§ããããæ¢ç³è¾¼ã®ã¯ã«ã¼ãºããã£ã³ã»ã«ãããä¹ãæããæ¹ãä¸é¨ã«ã¯ããã£ãããã¾ããã
å¦å¥³èªæµ·ã«ããã第1åã®ã¯ã«ã¼ãºã¯ãæµç³ã«æ¬æ°éãã¦åã¯ã¹ã«ã¼ãã¾ãããããã®å¾2020å¹´ã®SOLASæ¡ç´※1ï¼æ¹æ£ã«å«ã¾ããè¹è¶ã®ç°å¢ã¸ã®å½±é¿ãUPAï¼United Peoples Allianceï¼※2ï¼ãªã©ã®æ´»åãç¥ããã¨ã«ãªãã第2åã3åã®åéããã£ããã«ã²ã¨å£ä¹ãã¾ãããç¬
※1ï¼æµ·ä¸ã«ããã人å½ã®å®å
¨ã®ããã®å½éæ¡ç´ã
※2ï¼æ¯æ´ç©è³ãä¸çä¸ã«å±ããæ´»åã
å人çã«ã¯ãæµ·å¤ã§ã®ã¯ã«ã¼ãºä½é¨ãããããã¸ã§ã¯ãã®é£ææ§ãèªèãã¦ããã2020å¹´å°±èªã¯éã«åããªãã ãããªã¨æã£ã¦ããã¾ããããä¸æ¹ã§ã欧å·ã®é è¹ããã»ã¹ããããå½ã®ããã¨ã¯ç°ãªããã¨ãç¥ãã¾ããã
欧å·ã§ã¯ãè¹è¶å»ºé ã¯åæ¥åããã¦ãããè¨è¨ã¯ã¨ã³ã¸ãã¢ãªã³ã°ä¼ç¤¾ãè¡ããããããããã¼ã¸ã¡ã³ããããã¢ã¸ã¥ã¼ã«ã製ä½ãå¹çåãããããã°ã©ã ã®æ¡ç¨ã«ãããã·ããã¤ã¼ãèªä½ãè¡ãä½æ¥ï¼å·¥ç¨ï¼ãæ¸ããããå·¥æã®ç縮ããã³çç£æ§ããåä¸※3ï¼ãããåãçµã¿ãé²ãã§ããã¾ãã®ã§ãä¸æ¦ã«ããå½ã®é è¹å¸¸èã以ã£ã¦å½ã¦ã¯ãããã¨ã¯ã§ãã¾ãããï¼ãããçµæçã«ãç³è¾¼è
ã¸ã®æ
å ±ä¼éã®é
ãã«ç¹ãã£ãããã§ããï¼
※3ï¼ä¾ãã°ãFincantierié è¹æã§ã¯2017å¹´ããã³2018å¹´ã«ããããã5é»ã®ç°ãªãCruise Lineã®å®¢è¹ã竣工ããã¦ããã¾ãã
ã¨ã¯è¨ãã2020å¹´1æ1æ¥çºå¹ã®æ°ããSOLASæ¡ç´ãã¯ãªã¢ããã®ã¯å®¹æã§ã¯ããã¾ããã
ãã¤ã³ãã¯ããã£ããçææ²¹ã®ç¡«é»åæ¿åº¦ãä¸ããç°å¢ã«é¢ããè¦å¶ã¨ãæ
客è¹ã®æå·æ復åæ§åºæºã®å¼·åã«ä¼´ãåºç»ã¨æå·æã®å¾©å
æ§è¦ä»¶ã®æ°è¨ã«çµããã¾ãã
åè
ã¯å
ã
ãä¸çã§æãå°çã«ããããè¹ããã³ã³ã»ããã«ãã¦ããã®ã§ããã¦åé¡ã§ã¯ãªãã§ãããããå¾è
ã¯è¹ç´åä¼ï¼DNV GLï¼ã«ããããã®å¤å®ãå«ããåä¾ããªããã¨ã§ãããæ³å®ãè¶
ããè¦å´ãããããã§ãã
éãæªããã¨ã«ãIMOï¼å½éæµ·äºå±ï¼ç¬¬96åæµ·ä¸å®å
¨å§å¡ä¼ï¼MSC96ï¼ãã審è°ããã¦ããåºç»ã¨æå·æã®å¾©å
æ§è¦ä»¶ãæ¡æãããã®ã¯2017å¹´6æã«ãã³ãã³ã§éå¬ãããIMO第98åæµ·ä¸å®å
¨å§å¡ä¼ã«æ¼ãã¦ã§ãããeco shipã®ãã©ã³ãåºã¾ãåéãéå§ãããã®ã2015å¹´ã®9æï¼ãã®æç¹ã§ã¯ãé è¹æãé¸å®ä¸ã§ããã¨è¨ããã¦ããï¼ã§ãã£ãããããã®å¾è¨è¨å¤æ´ãä½åãªãããã※4ï¼ãã¨ã¯æ³åã«å¤ãã¾ãã
※4ï¼2020å¹´1æ1æ¥ä»¥åã«å¥ç´ãç· çµãã¦ããè¹è¶ã«ã¤ãã¦ã¯ãIMO98ã§æ±ºã¾ã£ãæ°ã«ã¼ã«ã¯é©ç¨ãããã建é ãããã¨ãã§ãã¾ãã
ãããæ°é è¹ã®å®å
¨æ§åä¸ã«è³ãããã¨ã§ãããå°é家ããSOLAS2020ãé©ç¨ãããã¨ãå©è¨ãããçµæç´æã¸ã®å½±é¿ãå諾ããããå¾ãªãã¨ã®å¤æããã£ãããã§ãããæå³ãããããç©ã¿éãããæ´å²ã«å»ã¾ããè¹ãè²ã¦ã¦è¡ãã®ã ãããªã¨æãã¾ãã
ä¸å£ã¡ã¢











 åãã¦é¨ãéã£ãããåå¾ã«ã¯æ¥ãå·®ãããã¤ãã®ããã«æ¥ãæµ´ã³ï¼ãã¸ã ã«éã£ãã
åãã¦é¨ãéã£ãããåå¾ã«ã¯æ¥ãå·®ãããã¤ãã®ããã«æ¥ãæµ´ã³ï¼ãã¸ã ã«éã£ãã